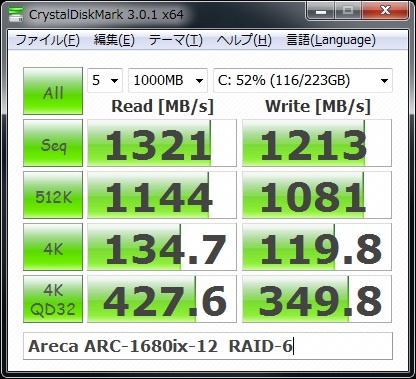 sambaの事は、もう忘れちゃいましたし、ZFSの事は未だ使った事がないのですが、 sambaの事は、もう忘れちゃいましたし、ZFSの事は未だ使った事がないのですが、
ZFS上の断片化と、samba(sambafs?)上の断片化に加え、ディレクトリ構造(B+Tree)の断片化の三重構造的な断片化が起きてるのではないか?という気がしますが、
>たとえばExplorerで同じディレクトリ(20万ファイル、15000ディレクトリ、660GB)のプロパティを表示する場合。
つまりネット越しにランダムアクセスって事ですよね。
試しに、現/新ネットワークドライブに対してCrystalDiskMarkを実行してみては?
遅い原因の切り分けが出来そうな気がします。
CrystalDiskMarkの結果にそれほど違いが無い場合は、ディレクトリ構造(B+Tree)の断片化が主な原因の可能性が高そうだと思いますし、
CrystalDiskMarkの結果がディレクトリのプロパティ同様の結果ならZFS上の断片化ではないでしょうか?
いづれにしろ、ランダム/シーケンシャルの両方或いは片方だけ差が出たなら、
それを元に推測できそうな気がします。
>$time du -s testdir
ってことは、ZFS上のディレクトリを管理してるツリー構造が断片化(つまり、
ランダムアクセスを強要される)してるか、或いは履歴関係(ファイルを以前の
状態に戻せる様にしていた場合ですが)の履歴保存に使われてる容量計算で厄介
な事が起きてるのかも?
ddコマンドでHDDをまるごとコピーして全く同じ構成で比較してみてどうなるか?にも興味ありです(たぶん、遅い。もし遅くなければ現サーバではハード的なリトライが頻発してる)
ていうかArecaのRAID-6は早いですよ~
左の画像は1年以上メインでほぼ毎日使ってる13号機のシステムドライブを今日測定したものです。
デフラグは一度もしてませんが、ExplorerでC:\Windows(9万ファイル/19,900フォルダ、20GB)のプロパティ表示が3秒でした。こいつはSSDを6台でのRAID-6です。
他に、過去10年以上の仕事データをバックアップしてあるフォルダで計測してみました。
色々な経緯から数年前にWD緑2TのRAID-1構成に移し変えたのですが、50万ファイル/43,223フォルダ/690GBのプロパティ表示が2分6秒でした。
しかしWin7のシステムフォルダには、なんであんなに多量にディレクトリが有るんでしょうかね?最近何かの記事で読んだ気もしますが忘れちゃいましたw
(*.zoot.jp)
|